
|
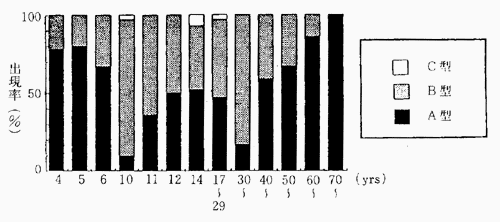
図15 脊柱伸展パターンの年齢による変化。
性を調査し、7〜11歳で急増し15歳でピークになること、その後は低下し、60歳以降は急減すると報告している。本論の低下率はこれら報告に比べて低い。一方、成人女性の長座体前屈には、若年・中年・高年に有意な差がないという岩岡ら2)の報告もある。また、小林ら7)は、中高年の体操教室参加者で、6ヵ月後に屈曲度の向上がみられたことを報告している。したがって、本論の対象の水泳教室や体操教室参加といった運動習慣が加齢退行を防いでいると考えられる。
(2) 伸展度の年齢推移
伸展パターン(図15)からみると、全体を通し、耳珠点(A)が高いA型、ついで胸高いB型が多く、頭部を高く保ったまま伸展運動をすることがわかる。また幼児期にもA型が多く、加齢にともないA型が増すが、伸展度のピークは、10〜11歳にB型の増加、さらに30歳頃に2次的なピークがみられる。これまでの報告では、伸展度のピーク年齢は単峰性のもの9)、双峰性のもの16)、多峰性のものなどさまざまで、ピーク該当年齢や年齢推移にもばらつきがある。これには弯出部位の個人差や年齢差が影響していると思われる。
図16は『角B』『角C』『角D」『角E』の年齢推移を示したものである。部位別伸展度(伸展度は伸展角と逆になっている)の平均曲線をみると、『角B」『角C」型と『角D』『角E』型に分類でき、10歳から20歳以後は『角B』『角C』は漸増するが、『角D』『角E』に大きな年齢差はない。
平均値のピーク年齢は『角B』で10歳、『角C』で5歳、『角D』で10歳、『角E』で14歳となり、『角C』は幼児期に、『角B」『角D』『角E』は10〜14歳に可動性が高くなる。また、思春期までは平均値曲線にいくつかのブレイクがあり、伸展動作にもいくつかの特徴的な型がみられた(後述)。部位別の年齢推移をみると、40歳以降は『角B』つまり頭部伸展角の減少が著しい(図16)が、これについては山下ら20)の報告と一致する。全体を通じ、年齢にともない、優位な伸展部位が頭方から尾方に移るといえる。
個々の伸展姿勢の年代的特徴をみると、10歳ごろに多くみられるのは『角B』『角C』の可動性の大きい、いわゆる胸反り型で(図17)、ちょうど、植物の“ぜんまい”のように、下肢をのばしたまま、上体が伸展し、上部脊椎と胸部前面の柔軟性をうかがわせる。この型は14歳までは、各年齢で30%程度みられたが、14歳で7%、それ以後はほとんどなくなり、かわりに『角C』(胸)や『角D』
(ウエスト)の反りがつよい型がふえる。『角C』『角D』の伸展が優位な型は、14歳の60%から20歳代では18%に減る。一方、30歳以降では、図17,18にみられるように、伸展度の低下を膝・足関節の屈曲で補償した姿勢が80%以上をしめる。
図19は伏臥位で上体おこしを、上段は足首を押さえて、下段は押さえなしで行った場合である。
7歳児では肋骨下部を支点に、それより頭方よりの脊柱起立筋で上体がもちあがっているため、補助の有無による差異のすくない事例が多い。一方、中年期には腸骨前上棟や恥骨を支点に、上体が持ち上がり、脊椎下部や骨盤帯の筋群が優位に活動している。これらの筋群は下肢の伸展と上体の伸
前ページ 目次へ 次ページ
|

|